安全への取り組み
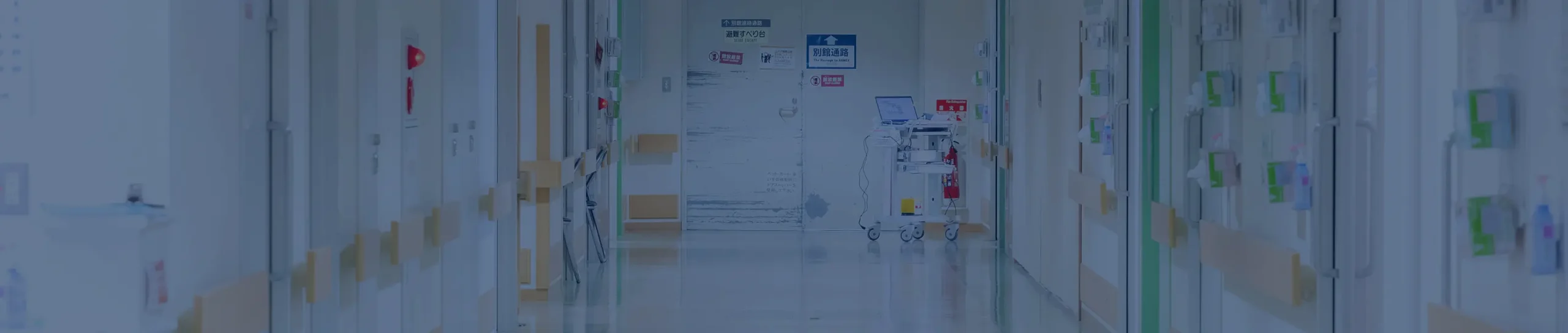
医療安全管理室
医療安全は、医療の質に関わる重要な課題です。安全な医療を提供するためには何が必要か考え、そのための方策を実行し、医療安全の体制を整えることが重要になります。
その実務を担当するのが医療安全管理室(医療安全管理指針)です。当院では専従の医療安全管理者を置き、安全で質の高い医療を提供することを目標に、以下の活動をしています。
組織と体制
当院の医療安全管理体制は、病院全体の医療安全を管理・指揮する医療安全管理委員会、各部署のリスクマネージャーが構成員となり安全な医療について検討を行なう医療事故防止委員会、医療安全管理室(医療安全管理指針)からなっています。医薬品や医療機器の安全管理責任者、感染対策委員会、その他各委員会とも連携し、医療安全の体制を整備しています。
インシデント・アクシデントレポート
医療事故(アクシデント)が発生した場合は、速やかに報告・対応・調査・分析するために、報告制度を定めています。この報告制度には、事故に至らないまでのヒヤッとした事、ハッとした事例や軽微な事故(インシデント)も含まれます。これらの報告をもとに、業務手順の見直しやシステムの構築をはかり、医療事故の防止に努めています。
医療安全管理室の主な業務
安全な医療を提供するための医療安全体制の整備
医療安全に関する指針やマニュアルの整備、各委員会への医療安全面からのサポート、患者様からの苦情や要望等の分析および活用のための患者相談窓口の設置、安全管理のための職員研修等の実務を担当しています。
また、各部署にリスクマネージャーを配置し、インシデント報告の推進と報告事例の収集・分析・対策を一緒に行なうことのできる体制を整備しています。
院内の各スタッフへの働きかけ
病院内には医師、看護師の他に、薬剤師や技師(検査技師、放射線技師、臨床工学技士等)、リハビリテーションスタッフ、栄養管理士など様々な専門職種とその他事務部門が存在し、チーム医療を基本としています。個人のレベルもベテランから新人まで幅広い人材の集合体であり、一般の企業に比べるとスタッフの入れ替わりも多いため、すべてのスタッフに標準業務手順書を周知徹底することの難しさを痛感しています。
医療安全管理者は、各現場と密接に連携をとりながら、業務が安全に行なわれているかを定期的に院内巡視し、ルール遵守の管理をしています。
実際に事故が起きた場合の適切な対応
病院では事故が起きないよう最善の努力をしておりますが、万が一のことも想定しておかなければなりません。事故が発生した場合は、医療安全報告システムにより速やかに情報の収集・分析を行い、医療事故予防策・再発防止策の立案、実施、評価および見直しを行ないます。
有害事象が発生した場合や重大事故発生時などは、事故対策本部を設置し事情を調べ、医療安全管理者が窓口となる役割も担っています。当院は、事実経過や原因の調査に全力を尽くします。また、その結果については、患者様やご家族に誠意をもってお話していく考えです。
欠かせない患者様一人一人のご協力
医療安全のための当院の取り組みの一端をご紹介しましたが、実は、その徹底には、患者様お一人お一人のご協力を欠かせません。医療事故はどんなに万全な対策を立てても決してゼロにはなりません。人間の情報処理能力には限界があり人は必ず間違いをおかします。そして、医療の現場にはエラーを誘発しやすい要因がたくさんあります。医療事故から身を守るためにも、患者様自身が医療チームの一員となり、医療に参加されることが重要です。
安全な医療を提供するための医療安全体制の整備
医療安全に関する指針やマニュアルの整備、各委員会への医療安全面からのサポート、患者様からの苦情や要望等の分析および活用のための患者相談窓口の設置、安全管理のための職員研修等の実務を担当しています。また、各部署にリスクマネージャーを配置し、インシデント報告の推進と報告事例の収集・分析・対策を一緒に行なうことのできる体制を整備しています。
患者様にお願いしたいこと①:安全確認
採血、輸血、抗がん剤の投与、点滴や投薬などの与薬業務、手術などのさまざまな場面において、患者の取り違えが発生した場合は重大な事故につながります。当院ではご本人確認のために患者様にお名前を名乗っていただくことを基本としているため、何度もお名前を聞かれることがあると思います。
医療スタッフが呼んだ名前は本当にあなたのお名前でしょうか?患者間違いを防ぐためにも、フルネームではっきり名乗っていただくことと、入院中はネームバンドの提示にご協力をお願いします。
患者様にお願いしたいこと②:ちょっと待っての一言を
医療の現場ではさまざまな安全確認が行われていますが、病院には間違いを起こしやすい要因がたくさんあります。何かおかしいと思ったとき、患者さんの「ちょっと待って」の一言が医療事故を防ぎます。
- 名前が似ている:同姓・同名、カタカナや漢字で書くと似ている、声に出すと似ているなど
- 外見が似ている:顔、体型、年齢など
- 状態が似ている:疾患が同じ、薬剤が同じ、入院日が同じ、ともに緊急入院など
- ベッドの位置が似ている:違う部屋の同じ位置、個室で隣同士など
その他の取り組みについて
上記のほか、患者様・ご家族の医療参加のための10の項目をお願いしています。
詳細はクリックしてご覧ください。
また、当院の地域連携室では、患者様向けの医療安全推進を目的に、定期的に健康講座を開催しています。こちらへの参加もぜひお願い致します。
医療安全管理指針
安全管理に関する基本的考え方
安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、職員ひとりひとりが医療安全の必要性・重要性を自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り、安全な医療の遂行を徹底することが重要です。
東京西徳洲会病院はこの考えの下に、医療従事者の個人レベルの対策とともに、病院全体の組織的な対策を推進することによって事故を防止し、患者様が安心して安全な医療を受けられる環境を整備することを目標としています。
安全管理のための組織および体制
当院の医療安全管理体制は、病院全体の医療安全を管理・指揮する医療安全管理委員会、各部署のリスクマネージャーが構成員となり事故防止について検討を行う医療事故防止委員会、専従の医療安全管理者が実務を担当する医療安全管理室(医療安全管理指針)からなっています。
医療事故等発生時の対応に関する基本指針
- 認知した医療事故については、速やかに必要な回復措置を講じます。
- 事故の状況及び必要な措置について、患者様やご家族に説明の上承諾を得るとともに、事実関係を記録します。
- 突発的に致死的心肺・脳障害に陥った患者様に対しては、院内救急コールの出動を要請し救命措置に勤めます。
- 医療事故の防止および医療トラブルの円滑な解決に資するため、医療事故(ニアミスを含む)および医療トラブルは院長に報告し、院内連携を図るよう努めます。
医療従事者と患者さまとの間の情報の共有に関する基本方針
患者様からご要望があった場合、およびその他必要な場合は、「医療に係る安全管理のための指針」が閲覧できます。
患者さまからの相談への対応に関する基本方針
「患者相談窓口」を設置し、適切に対応します。
その他医療安全の推進のために必要な基本指針
職員は、インフォームド・コンセントを徹底し、患者様やご家族と良好な人間関係の醸成に努め、必要とされる注意義務を履行するとともに、確認を励行し、関係者間の連携を密にして患者様中心の安全な医療の提供に努めます。
